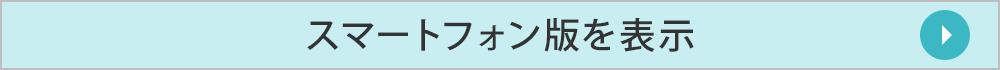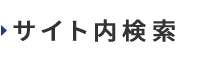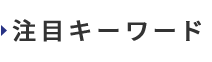国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)について
65歳から74歳までの世帯主の方であって、下記の1~3のすべてに当てはまる方は、年金から保険税を差し引いて納めていただくことになります。
1.年金から徴収される方
- 世帯に属する国保加入者全員が、65歳以上から75歳未満であること
・世帯内に65歳未満の方がいる場合⇒該当しません
・世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合
75歳以上の方が世帯主となっている場合⇒該当しません
75歳以上の方が世帯主となっていない場合⇒該当します - 年額18万円以上の年金(担保等により融資を受けている方等を除く)を受給している。
- 国民健康保険税と介護保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超えていないこと。
| 番号 | 例 | 徴収方法 | 備考 |
| 例1 | 世帯主(夫)72歳:年金受給有り 世帯員(妻)68歳:年金受給有り |
特別徴収 | 2名とも国保加入者で、かつ65歳以上であるため、特別徴収の対象となります。 |
| 例2 | 世帯主(夫)72歳:年金受給無し 世帯員(妻)68歳:年金受給有り |
普通徴収 | 世帯主(夫)が年金受給者でないため、普通徴収対象となります。世帯主以外からの年金からは特別徴収されません。 |
| 例3 | 世帯主(夫)72歳:年金受給有り 世帯員(妻)68歳:年金受給有り 世帯員(子)33歳 |
普通徴収 | 世帯員(子)が65歳未満のため、普通徴収対象となります。 |
| 例4 | 世帯主(夫)78歳:年金受給有り 世帯員(妻)72歳:年金受給有り |
普通徴収 | 世帯主(夫)が75歳以上で後期高齢者医療制度対象のため、普通徴収対象となります。 なお、支払は妻1名分となります。 |
| 例5 | 世帯主(夫)72歳:年金受給有り 世帯員(妻)78歳:年金受給有り |
特別徴収 | 世帯主(夫)が65歳以上75歳未満で、妻は後期高齢者医療制度対象のため、特別徴収対象となります。 なお、支払は世帯主(夫)1名分となります。 |
| 例6 | 世帯主(夫)72歳:年金受給有り 世帯員(妻)68歳:年金受給有り 世帯員(子)33歳 (5月国保加入) |
特別徴収 普通徴収 併用 |
夫、妻2名とも国保加入者で、かつ65歳以上であるため、特別徴収の対象となっておりましたが、65歳未満の子が加入したことにより、特別徴収から普通徴収へ切り替わることになります。 なお、普通徴収への切り替え時期によっては、子が国保加入後も特別徴収が継続される場合があります。 |
2.特別徴収の対象となる年金
国民年金・厚生年金などの老齢・障害・遺族年金などで、介護保険が特別徴収されている公的年金となります。
3.特別徴収する額
4月・6月・8月に支給される年金からは、前年度の保険税額(12か月分計算)を基礎として、仮の保険税額を徴収し、10月・12月・翌年2月に支給される年金からは、今年度の確定保険税額と仮徴収保険税額の差額を徴収します。
例:前年度保険税120,000円、本年度保険税150,000円の場合
仮徴収額(4月・6月・8月に徴収する額)
120,000円÷6=20,000円(仮徴収額)
本徴収額(10月・12月・翌年2月に徴収する額)
150,000円-60,000円(仮徴収額)=90,000円÷3=30,000円(本徴収額)
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 合計 |
| 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年05月09日