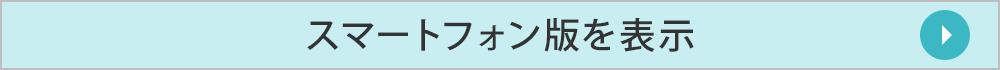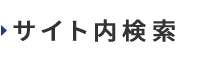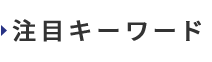認知症初期集中支援事業について
認知症の患者数
内閣府の高齢社会白書によると、認知症の高齢者数は令和4年時点で約443万人、認知症の手前の状態である、軽度認知障がい(MCI)と呼ばれる症状がある認知症予備軍は約559万人います。(現在の医療では認知症を完治させられませんが、軽度認知障がい(MCI)は心身の活性化により、それ以前の正常な状態に戻ることも可能と言われています)
認知症やMCIの高齢者数が令和7年以降も一定と仮定すると、令和22年には認知症高齢者は約584万人、MCI高齢者は約613万人になると推計されており、地域での認知症対策が急務となっています。
認知症とは
認知症とは病名ではありません。病気によって生じる症状や状態のことをさします。認知症の原因となる病気は数多くありますが、代表的なものは次のとおりです。
◎神経変性疾患
・アルツハイマー型認知症
・レビー小体型認知症
・前頭側頭型認知症
◎脳血管性認知症
◎その他
・正常圧水頭症
・脳腫瘍
・慢性硬膜下血腫
・栄養障害
・甲状腺機能低下症 など
「◎その他」で挙げた病気は治療により良くなる可能性のある認知症です。認知症はこれらのケースを除いて完治しませんが、進行を遅らせることは可能です。よく、薬を飲んでいればいいという方がいますが、大切なのは本人の生活習慣です。糖尿病や高血圧などの生活習慣病を予防し、睡眠や適度な運動も心がけることが必要です。
もしかして認知症?
年齢を重ねると人の名前がとっさに出てこない、何を買おうとしたのか思い出せないなどといったことが増えてきます。これは加齢に伴う自然な物忘れで「良性健忘症」と呼ばれています。
認知症の初期症状は物忘れから始まることが多いですが、日常生活の中では調味料の分量の感覚がわからなくなって料理の味が変わったり、同じものを何度も買ってきて冷蔵庫の中で腐らせたりしまったりするなど、生活上で異変が現れます。車を運転する方は車庫入れや駐車で車をこすったり、蛇行運転をするようになることもあります。
また、幻覚、妄想、暴言、不眠、徘徊、異食などの周辺症状と呼ばれる状況が出ることもあり、症状によっては専門的な治療が必要となるケースもあります。
介護する側の支援も
治療と同時に、家族への支援も重要です。介護者が楽な気持ちでいなければ、優しく接して介護することはできません。
例えば、日中はデイサービスを利用し、少しでも介護する側が自分の時間を持てると心に余裕が生まれ、お互いの関係性が良くなることもあります。
認知症初期集中支援チーム
根室市では、平成30年4月に、認知症初期集中支援チームを『根室共立病院』に委託しました。
この支援チームは、市役所の地域包括支援センターが中心となり、医療や介護の必要性が高く、自ら支援を受けることが難しい方などに対し、看護師や社会福祉士などの複数の専門職が自宅を訪問し、認知症に関する相談や認知症の検査、その後の治療方針の検討など、認知症の方が住み慣れた地域で生活していけるよう支援を行っています。
認知症の症状があり、家族や地域の方が対応に困っているケースなどがありましたら、市役所の地域包括支援センターにご相談ください。また、根室共立病院でも相談を受け付けています。
認知症の人への対応の心得(3か条)
● 驚かせない
突然後ろから声をかけたりせず、ゆっくり近づいて相手の視野に入ってから声をかけましょう。
●急がせない
一度にたくさん話しかけたり複数で囲んだりせず、聞き手の反応を伺いながらゆっくりと会話をしましょう。
●自尊心を傷つけない
失敗を責めたり叱ったりせず、気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
認知症は決して他人事ではありません。だからといって不安になるのではなく、まずは認知症について学び、理解していくことが重要です。そして、家族だけでなく、地域全体で認知症を理解し見守ることで、みんなが安心して暮らせる地域社会を築くことができるはずです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部介護福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692介護福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月10日