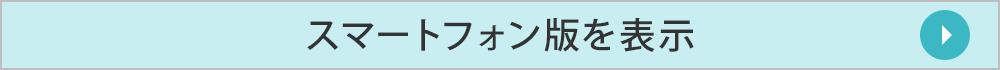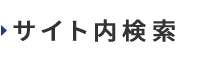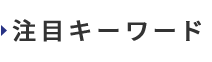令和6年度 保健だより8月号「健康に配慮した飲酒」
「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」
厚生労働省は、適切な飲酒量・飲酒行動の判断を促す「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成し令和6年2月に公表しました。
厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて」
飲酒量は、純アルコール量に換算して把握しましょう
お酒によってアルコール度数が異なるため、自分がアルコールをどれくらい摂取したか把握するためには、純アルコール量(g)に着目することが大切です。
お酒に含まれる純アルコール量の計算は下記の通りです。
▼「摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコール比重)」
例:ビール500ml(5%)の場合の純アルコール量
500ml×0.05×0.8=20g
飲酒量と健康リスク
国の健康づくり計画『健康日本21(第3次)』では、生活習慣病リスクが高まるとされる純アルコール量「1日当たり男性40グラム以上、女性20グラム以上飲む人を減らす」ことを目標にしています。
※純アルコール20g相当は各種アルコール飲料に換算すると、
| 種類 | 度数 | 量 |
| ビール | 5% | 500ml ロング缶 |
| チューハイ | 7% | 350ml |
| ワイン | 12% | 200ml 小グラス2杯 |
| 日本酒 | 14% | 180ml 1合 |
| 焼酎 | 25% | 100ml |
| ウイスキー | 43% | 60ml ダブル |
お酒の影響を受けやすい要因
1.高齢者:体内の水分量の減少等で、若いころと同じ飲酒量でもアルコールの影響が強く現れ、飲酒による転倒、骨折、筋肉の減少の危険性が高まります。
2.若年者:10代はもちろん20歳代の若年者についても脳の発達の途中であり、健康問題のリスクが高まる可能性があります。
3.女性:女性は、一般的に男性と比べて体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も少ないため、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。
4.体質の違い:体内の分解酵素のはたらきの強弱は個人によって大きく異なります。人によって、飲酒により顔が赤くなったり、動悸や吐き気を引き起こす場合があります。そのような体質の人が徐々に飲酒できるようになった場合でも、アルコールを原因とする口の中のがんや食道がんのリスクが高くなるというデータがあります。
健康に配慮した飲酒の仕方
・自らの飲酒状況を把握する
・あらかじめ量を決めて飲酒する
・飲酒前または飲酒中に食事をとる
・飲酒の合間に水を飲む
・1週間のうち、飲まない日を設ける
避けるべき飲酒や飲酒後の行動
・一時多量飲酒(特に短時間の多量飲酒)
・他人への飲酒の強要
・不安や不眠を解消するための飲酒
・病気など療養中の飲酒や服薬後の飲酒
・飲酒中または飲酒後の運動や入浴
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部健康推進課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692健康推進課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月01日