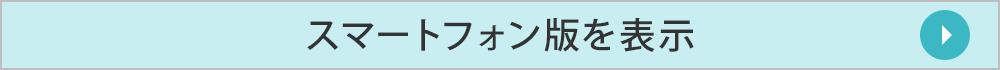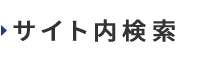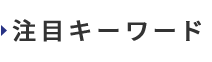土器
穂香竪穴群出土の動物意匠付土器
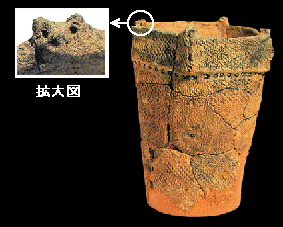
根室市穂香で発掘された縄文時代後期初頭(約4,000年前)の土器。上部4箇所に一部は熊と考えられる顔が 付けられています。動物意匠が付けられた土器は道東ではこの土器が最も古いものです。
根室市指定有形文化財
写真:北海道立埋蔵文化財センター提供
擦文時代の土器

11~12世紀頃の擦文時代後半の土器です。擦文土器は一般的に幾何学的な線による文様がみられます。
擦文時代の遺跡は竪穴住居跡が凹みとなって地表から確認できます。
おもに土器で煮炊きをするという縄文時代からの文化は擦文時代で終わることから、擦文文化は日本最後の土器文化として知られています。
(西月ヶ岡遺跡出土)
オホーツク土器

オホーツク土器の中でも貼付文(はりつけもん)土器とよばれるものです。8~9世紀頃のものと考えられています。土器の装飾に細い粘土紐を貼り付けています。
(トーサムポロ湖周辺竪穴群出土)
写真:北海道立埋蔵文化財センター提供
縄文時代前期の土器

縄文時代前期(約5,500年前)の土器で、「温根沼(おんねとう)式」とよばれています。
温根沼は根室半島の基部にあたる湖の名前で、その東岸に位置する関江谷1竪穴群で最初に発見されたので、温根沼式という名称がつけられました。
土器の底が尖っており、木片に刻みをつけたものや縄をスタンプのように押しつけて文様としているのが特徴です。
(トーサムポロ湖周辺竪穴群出土)
写真:北海道立埋蔵文化財センター提供
縄文時代早期後半の土器

縄文時代早期後半(約7,500年前)の土器で浦幌式(うらほろしき)土器とよばれています。現在のところ、根室市内で一番古い土器であるとされています。
上からみると土器の口縁が隅丸方形で、植物質の軸に撚り糸を巻き付けて道具を押し当てて、口縁部に縄文をつけているのが特徴とされています。
(トーサムポロ湖周辺竪穴群出土)
写真:北海道立埋蔵文化財センター提供
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月01日